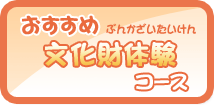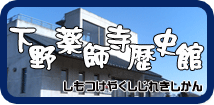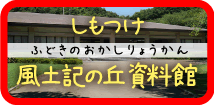時代名をクリックし詳しい年表をご覧ください。

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - -10000年
(紀元前) ・祇園、緑地区付近で石器が作られた
・国分寺付近で黒曜石(こくようせき)のナイフ形石器を使う
・両面加工尖頭器(りょうめんかこうせんとうき)を使う三ノ谷東・谷館野北遺跡
国分寺山王遺跡
薬師寺南遺跡

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - -9000年
(紀元前) 爪形文土器(つめがたもんどき)を使った煮炊(にた)きをする
薬師寺稲荷台(やくしじいなりだい)遺跡
- -8000年
(紀元前) 撚糸文系(よりいともんけい)の土器を使用
海が広がり、野木町や栃木市藤岡町周辺が海岸線となる
烏ケ森(からすがもり)遺跡
- -2500年
(紀元前) 国分僧寺(こくぶんぞうじ)付近に住居(じゅうきょ)がつくられる
国分僧寺下層(こくぶんそうじかそう)遺跡
- -2000年
(紀元前) 絹板(きぬいた)地区にムラができる
絹板大六天(きぬいただいろくてん)遺跡
- -1500年
(紀元前) 坪山(つぼやま)地区にムラができる
西原南(にしはらみなみ)遺跡

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - -300年
(紀元前) 柴地区に再葬墓(さいそうぼ)がつくられる
(土器に籾(もみ)の跡(あと)があるため、米がつくられていたことがわかる)柴工業団地内遺跡
- -100年
(紀元前) 稲作(いなさく)を行うムラができる
烏ヶ森(からすがもり)遺跡、上芝(かみしば)遺跡、谷館野北(やだてのきた)遺跡、谷館野東(やだてのひがし)遺跡
- 0年
(頃) 諏訪山遺跡で土器を使った墓(はか)がつくられる
諏訪山(すわやま)遺跡
- 100年
(頃) ムラの中に鉄剣(てっけん)を持つ人物がいた
三王(さんのう)遺跡

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 300年
(4世紀はじめ) 三王山(さんのうやま)に前方後方墳(ぜんぽこうほうふん)がつくられる
- 400年
(5世紀ごろ) 自治医科大学南方にムラができるが、水田の開発に失敗したため、離散(りさん)したと考えられる
烏森(からすがもり)遺跡
- 500年
(6世紀ごろ) 姿川(すがたがわ)西側にムラができる
箕輪館(みのわだて)遺跡
- 538年
朝鮮半島(ちょうせんはんとう)の百済(くだら)より仏教が伝わる
- 550年
(6世紀後半) 市内に大型の前方後円墳(ぜんぽうこえんふん)がつくられたほか、周辺にも古墳がつくられた
- 600年
(7世紀はじめ) 市内で最後の首長墓が造られる

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 604年
聖徳太子(しょうとくたいし)が17条憲法を定める
- 645年
(大化元年) 大化の改新(乙巳の変・いっしのへん)
- 673年
下野薬師寺(しもつけやくしじ)がつくられる
- 687年
朝鮮半島(ちょうせんはんとう)からきた新羅人(しらぎじん)を下野国(しもつけのくに)におく
このころ東山道がつくられる
- 694年
藤原京(ふじわらきょう)に都(みやこ)をうつす
- 700年
・那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)がたてられる
・このころ下野国府(しもつけこくふ)ができる- 701年
(大宝元年) 下毛野古麻呂(しもつけぬのこまろ)が、大宝律令(たいほうりつりょう)の選定(せんてい)にかかわる
- 705年
(慶雲2年) 下毛野古麻呂(しもつけぬのこまろ)、兵部省(ひょうぶしょう)の長官となる
- 707年
(慶雲4年) 下毛野古麻呂(しもつけぬのこまろ)、文武(もんぶ)天皇の陵墓(りょうぼ・お墓のこと)をつくる担当者となる
- 708年
(和銅元年) 下毛野古麻呂(しもつけぬのこまろ)、式部省(しきぶしょう)の長官となる
- 709年
(和銅2年) 下毛野古麻呂死去

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 710年
(和銅3年) 都(みやこ)を平城京(へいじょうきょう)にうつす
- 714年
(和銅7年) 下野国(しもつけのくに)などが、大風の被害により、租調(そちょう・税金)を免除(めんじょ)される。
- 741年
(天平13年) - 745年
(天平17年) 奈良の東大寺で大仏をつくりはじめる
- 749年
(天平勝宝元年) 下野薬師寺(しもつけやくしじ)の墾田(こんでん)が500町(約500ha)と定められる
- 754年
(天平勝宝6年) 薬師寺の僧(そう)行信(ぎょうしん)、呪(のろ)いの罪で下野薬師寺に配流(はいる)される
鑑真(がんじん)が来日する
- 761年
(天平宝字5年) 下野薬師寺に戒壇(かいだん)が置かれる
- 765年
(天平神護元年) 下野国で飢饉(ききん) 下野国など5か国で干(かん)ばつの被害
- 770年
(宝亀元年) 道鏡(どうきょう)失脚(しっきゃく)し、造下野薬師寺別当(ぞうしもつけやくしじべっとう]として任じられる
- 772年
(宝亀3年) 道鏡(どうきょう)が亡くなり、庶民(しょみん)と同じように埋葬(まいそう)される
- 781年
(天応元年) 後に開雲寺(かいうんじ)となる東光寺(とうこうじ)下古山に創建(そうけん)したと伝えられる
開雲寺(かいうんじ)

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 794年
(延暦13年) 都(みやこ)を平安京(へいあんきょう)に移す
- 801年
(延暦20年) 征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)の軍が、市内の東山道(とうさんどう)を通る
- 818年
(弘仁9年) この年、関東で地震があり、大きな被害(ひがい)を受ける
- 875年
(貞観17年) 清和(せいわ)天皇により薬師寺八幡宮が建てられたと伝わる
- 935年
(承平5年) 承平(じょうへい)・天慶(てんぎょう)の乱(らん)
- 939年
(天慶2年) 下野国分寺、平将門(たいらのまさかど)に焼かれたとの伝説
平将門(たいらのまさかど)が下野国府(しもつけこくふ)を攻撃し占領する
- 940年
(天慶3年) 平将門(たいらのまさかど)、平貞盛(たいらのさだもり)、藤原秀郷(ふじわらひでさと)の軍に敗れる
秀郷、下野国守(しもつけこくしゅ)となる- 1092年
(寛治6年) 下野薬師寺の住僧(じゅうそう) 慶順(けいじゅん)、東大寺に下野薬師寺の復興(ふっこう)をもとめる
慶順
- 1100年
(11世紀末頃) - 1108年
(天仁元年) 浅間山(あさまやま)の噴火(ふんか)により市内でも灰が降る
浅間山(あさまやま)が噴火(ふんか)

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1185年
(元暦2年) 平家(へい)、壇ノ浦(だんのうら)で滅亡(めつぼう)
- 1188年
(文治4年) 源頼朝(みなもとのよりとも)、吉田八幡宮(はちまんぐう)を建てると伝わる
- 1192年
(建久3年) 源頼朝(みなもとのよりとも)が鎌倉(かまくら)に幕府(ばくふ)を開く
- 1195年
(建久6年) 源頼朝(みなもとのよりとも)、下野薬師寺に僧(そう)3人を加え武運長久(ぶうんちょうきゅう)をいのる
- 1196年
(建久7年) 新田義兼(にったよしかね)により慈眼寺(じげんじ)が建てられたと伝えられる
慈眼寺
- 1204年
(元久元年) 東根供養塔(ひがしねくようとう)が建てられる
- 1221年
(承久3年) 承久(じょうきゅう)の乱(らん)
下古舘遺跡(しもふるだていせき)
- 1229年
(~31年頃寛喜年間) この頃、薬師寺(小山)朝村(ともむら)が薬師寺城をつくる
- 1248年
(宝治2年) 宇都宮頼綱(よりつな)の四男宗朝(むねとも)が上三川町多功(たこう)に城をつくり多功氏を名乗る
- 1282年
(弘安5年) 多功宗朝(たこうむねとも)の子、朝定(ともさだ)が児山城(こやまじょう)をつくり、児山氏(こやまし)を名乗る
- 1283年
(弘安6年) 華蔵寺(けぞうじ)が、児永山大通寺光明院(じえいざんだいつうじこうみょういん)として建てられる。
華蔵寺(けぞうじ)
- 1289年
(正応2年) 下条民部太夫重慶(しもじょうみんぶだゆうしげよし)、坪山城(つぼやまじょう)をつくる
坪山城跡(つぼやまじょうあと)
- 1333年
(元弘3年) 鎌倉幕府(かまくらばくふ)滅亡(めつぼう)

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1334年
(建武元年) 建武(けんむ)の新政(しんせい)
- 1338年
(建武5年) 足利尊氏(あしかがたかうじ)が征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)となる
- 1339年
(暦応2年) 足利尊氏(あしかがたかうじ)が、下野薬師寺(しもつけやくしじ)を安国寺(あんこくじ)と改名したと伝わる
安国寺(あんこくじ)
- 1360年
(延文5年) 日行上人(にちぎょうしょうにん)がこのころ、後に蓮行寺(れんぎょうじ)となる金井法華坊(かないほっけぼう)を開く
蓮行寺(れんぎょうじ)
- 1380年
(康暦2年) 裳原(茂原)で宇都宮基綱と小山義政が戦い児山宗朝も参戦
- 1391年
(明徳2年) 鎌倉公方(かまくらくぼう)足利氏満(あしかがみつうじ)が薬師寺荘(しょう)の半分を鎌倉の別願寺(べつがんじ)に寄付する
- 1392年
(明徳3年) 南北両朝合一(なんぼくりょうちょうごういつ)
- 1430年
(永享2年) このころ金井宿(のちの小金井宿)ができる
- 1441年
(嘉吉元年) 坪山城、結城合戦により結城城とともに落城、廃城となる
- 1467年
(応仁元年) 応仁の乱
- 1502年
(文亀2年) 東光寺(とうこうじ)が現在の場所に移されて開雲寺(かいうんじ)となったと伝えられる
開雲寺(かいうんじ)
- 1538年
(天文7年) 宇都宮氏の家臣(かしん)芳賀高経(はがたかつね)が児山城に籠城(ろうじょう)する
- 1549年
(天文18年) 宇都宮氏と那須氏が喜連川(きつれがわ)で戦い児山城主児山兼朝(こやまかねとも)も出陣する(五月女坂の戦い)
児山兼朝(こやまかねとも)
- 1558年
(永禄元年) 児山城主(こやまじょうしゅ)・児山兼朝(かねとも)が上杉謙信との合戦で討死(うちじに)
児山兼朝(こやまかねとも)
- 1570年
(元亀元年) 北条氏(ほうじょうし)、結城氏(ゆうきし)との戦いにより下野薬師寺が全焼(ぜんしょう)したと伝えられる
- 1573年
(天正元年) 織田信長が将軍(しょうぐん)足利義昭(あしかがよしあき)を追放(ついほう)し室町幕府(むろまちばくふ)が滅亡(めつぼう)する

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1574年
(天正2年) 下野薬師寺の僧(そう)晃榮(こうえい)が薬師寺縁起(やくしじえんぎ)を記(しる)す
- 1575年
(天正3年) 元寿僧正(げんじゅそうじょう)が田中で生まれる
元寿僧正(げんじゅそうじょう)
- 1576年
(天正4年) 北条氏(ほうじょうし)の軍が、小山を攻略(こうりゃく)する
- 1582年
(天正10年) 本能寺(ほんのうじ)の変
- 1585年
(天正13年) このころ、宇都宮国綱(うつのみやくにつな)、本拠(ほんきょ)を宇都宮城より多気山城(たげさんじょう)へ移す
- 1590年
(天正18年) 豊臣秀吉(とよとみひでよし)により、北条氏(ほうじょうし)が滅亡(めつぼう)する
- 1591年
(天正19年) 徳川家康(とくがわいえやす)が、下野国(しもつけのくに)のお寺に田畑を寄贈(きぞう)する
- 1597年
(慶長2年) このころ児山城、薬師寺城が廃城(はいじょう)となる
- 1600年
(慶長5年) 関ヶ原(せきがはら)の戦い

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1603年
(慶長8年) 徳川家康(とくがわいえやす)が江戸幕府(えどばくふ)を開く
- 1605年
(慶長10年) 薬師寺・町田・田中・磯部・東根・仁良川・絹板・花田村が秋田(あきた)佐竹領(さたけりょう)となる
- 1617年
(元和3年) 江戸幕府(えどばくふ)により日光街道(にっこうかいどう)が整備(せいび)され、小金井と・石橋に宿場(しゅくば)ができる
このころ小金井一里塚ができる- 1619年
(元和5年) 将軍(しょうぐん)秀忠(ひでただ)が日光東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)する
- 1622年
(元和8年) 将軍(しょうぐん)秀忠(ひでただ)が、日光東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)する
- 1623年
(元和9年) 徳川家光(とくがわいえみつ)が日光東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)する
- 1625年
(寛永2年) 将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)が、日光東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)する
- 1628年
(寛永5年) 将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)と大御所(おおごしょ)秀忠(ひでただ)が、日光東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)する
- 1632年
(寛永9年) 将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)、父秀忠(ひでただ)喪中(もちゅう)のため今市で参拝(さんぱい)
- 1634年
(寛永11年) 将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)、東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)し、東照宮の改修工事(かいしゅうこうじ)をはじめる
- 1636年
(寛永13年) 日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)の改修工事(かいしゅうこうじ)が終了
将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)、東照宮(とうしょうぐう)を参拝(さんぱい)- 1642年
(寛永19年) 将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)、東照宮(とうしょうぐう)を社参(さんぱい)
- 1648年
(慶安元年) 将軍(しょうぐん)家光(いえみつ)、日光を参拝(さんぱい)する
- 1649年
(慶安2年) 宇都宮藩主(はんしゅ)奥平氏(おくだいらし)が開雲寺(かいうんじ)に御殿所(ごてんしょ)をつくる
大納言(だいなごん)家綱(いえつな)、日光を参拝(さんぱい)する- 1651年
(慶安4年) 鬼怒川(きぬがわ)舟運(ふなうん…舟で荷物を運ぶ)のため吉田に河岸(かし…船着き場)ができる
- 1659年
(万治2年) 壬生藩(みぶはん)が笹原新田(ささはらしんでん)を開発する
- 1663年
(寛文3年) 将軍(しょうぐん)家綱(いえつな)が、日光を参拝(さんぱい)する
- 1712年
(正徳2年) 壬生藩主(みぶはんしゅ)鳥居忠英(とりいただてる)により、かんぴょうが伝えられる
- 1724年
(享保9年) 吉田用水(よしだようすい)が完成する
- 1728年
(享保13年) 将軍(しょうぐん)吉宗(よしむね)が、日光を参拝(さんぱい)する
- 1763年
(宝暦13年) 薬師寺の馬市(うまいち)、下野国(しもつけのくに)を代表する馬市としてにぎわう(明治18年まで)
- 1776年
(安永5年) 将軍(しょうぐん)家治(いえはる)、日光を参拝(さんぱい)する
- 1807年
(文化4年) 仁良川村(にらがわむら)などの秋田藩領(あきたはんりょう)で百姓一揆(ひゃくしょういっき)がおきる
- 1816年
(文化13年) 小金井宿(こがねいじゅく)で放火(ほうか)事件があり、16軒が焼失(しょうしつ)する
- 1841年
(天保12年) 平田篤胤(ひらたあつたね)が仁良川村(にらがわむら)で国学(こくがくの講義(こうぎ)をする
- 1843年
(天保14年) 将軍(しょうぐん)家慶(いえよし)が、日光を参拝(さんぱい)する
- 1853年
(嘉永6年) ペリーが浦賀(うらが)に来航(らいこう)する
- 1867年
(慶応3年) 下古山村(しもこやまむら)・石橋宿(いしばしじゅく)で打ちこわし
- 1867年
(頃) 安国寺(あんこくじ)に六角堂(ろっかくどう)が建てられる

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1868年
(明治元年) 慈眼寺(じげんじ)で火事があり、ほとんどの建物を焼失(しょうしつ)する
明治維新(めいじいしん)
- 1871年
(明治4年) 廃藩置県(はいはんちけん)により栃木県と宇都宮県ができる
- 1872年
(明治5年) 小金井郵便局・石橋郵便局ができる
- 1873年
(明治6年) 教育舎(薬師寺)、化育舎(上吉田)、子来舎(上坪山)、啓蒙舎(石橋)、文明舎(上古山)、正倫舎(下古山)、時習舎(橋本)の各小学校が開校
栃木県と宇都宮県が合併し栃木県となる
- 1874年
(明治7年) 小金井学校、到高舎(川中子)の各小学校が開校
- 1875年
(明治8年) 磯東舎(磯部)、仁良川舎の各小学校が開校
- 1876年
(明治9年) 明治天皇(めいじてんのう)が巡幸(じゅんこう)のときに開雲寺(かいうんじ)で昼食をとる
- 1879年
(明治12年) 第1回栃木県会議員選挙が行われる
- 1881年
(明治14年) 明治天皇が巡幸(じゅんこう)を行い、開雲寺(かいうんじ)で昼食をとる
那須岳(なすだけ)が噴火(ふんか)
- 1883年
(明治16年) 三島通庸(みしまみちつね)、栃木県令(けんれい…現在の知事)となる
- 1884年
(明治17年) 加波山(かばさん)事件
- 1885年
(明治18年) 大宮~宇都宮間の東北本線が開通し、石橋駅が開業する
- 1889年
(明治22年) 姿村、国分寺村、吉田村、薬師寺村ができる
大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)ができる
- 1891年
(明治24年) 姿村(すがたむら)が石橋町と姿村に分かれる
- 1893年
(明治26年) 小金井駅が開業(かいぎょう)する
- 1894年
(明治27年) 日清戦争(にっしんせんそう)がはじまる
- 1904年
(明治37年) 日露戦争(にちろせんそう)がはじまる


-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1937年
(昭和12年) 日中戦争(にっちゅうせんそう)がはじまる
- 1938年
(昭和13年) 4代目の栃木県庁舎(とちぎけんちょうしゃ)ができる
- 1941年
(昭和16年) 太平洋戦争(たいへいようせんそう)がはじまる
- 1945年
(昭和20年) 宇都宮が空襲(くうしゅう)される
- 1947年
(昭和22年) 小平重吉(こだいらじゅうきち)、選挙(せんきょ)による初めての栃木県知事となる
- 1949年
(昭和24年) 今市(いまいち)で大地震(だいじしん)がおきる
- 1950年
(昭和25年) 警察予備隊(けいさつよびたい)、雀宮町(すずめのみや町)に駐屯(ちゅうとん)する
- 1954年
(昭和29年) 石橋町と姿村(すがたむら)が合併(がっぺい)し、石橋町となる
国分寺村が町になる- 1955年
(昭和30年) 吉田村と薬師寺村が合併(がっぺい)して南河内村となる
- 1965年
(昭和40年) 下野国分尼寺(しもつけこくぶんにじ)が国指定史跡(くにしていしせき)となる
- 1972年
(昭和47年) 自治医科大学(じちいかだいがく)が開校(かいこう)
- 1974年
(昭和49年) 自治医科大学(じちいかだいがく)附属病院(ふぞくびょういん)ができる
- 1975年
(昭和50年) 石橋町、ドイツのシュタインブリュッケンと姉妹都市(しまいとし)となる
- 1980年
(昭和55年) 栃木県で国体(こくたい)が開催(かいさい)される
- 1983年
(昭和58年) 自治医大駅(じちいだいえき)が開業(かいぎょう)する

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 1994年
(平成6年) テーマ館が開館
- 2006年
(平成18年) 南河内町、石橋町、国分寺町が合併し下野市となる
- 2011年
(平成23年) 道の駅しもつけがオープンする
- 2015年
(平成27年) 下野市立しもつけ風土記の丘資料館が開館
- 2016年
(平成28) 下野市新庁舎開庁
- 2017年
(平成29) 甲塚古墳出土遺物が国の重要文化財に指定される

-
- 西暦(元号)
- 下野市とその周辺に関すること
- 関連するできごと
- 市内の史跡
遺跡と人物 - 2021年
(令和3) しもつけ風土記の丘資料館リニューアルオープン