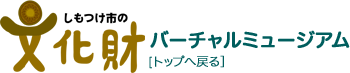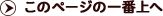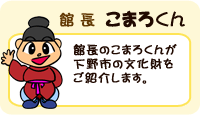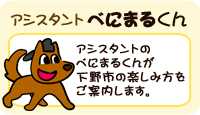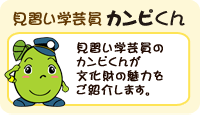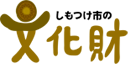東の飛鳥を楽しむ文化財体験コース
しもつけ古墳群めぐり(南河内・石橋地区)

このコースでは、南河内地区~石橋地区のしもつけ古墳群をめぐることができます。
しもつけ古墳群めぐり(南河内・石橋地区)
しもつけ古墳群は、古墳時代後期(6~7世紀)に造られた栃木県南部(下野市、栃木市、小山市、上三川町、壬生町)に所在する大型古墳(首長墓)群です。特徴として①古墳の墳丘に幅広い平坦面(基壇)を持つ、②凝灰岩の切石を組み合わせた横穴式石室を持つ、③前方後円墳は前方部のみに埋葬施設を持つが挙げられます。
なお、しもつけ古墳群とあわせて、県内最古級の前方後方墳である三王山南塚古墳群(南河内地区の三王山)の散策もおすすめし
※各スポット名をクリックすると解説や動画を見ることができます。
※GoogleMapの精度の関係で、マップと現地の位置に誤差が生じます。
ご了承の上でご利用ください。
史跡下野薬師寺跡探索コース

飛鳥時代に建立された下野薬師寺は、奈良時代前半には東国最大級の伽藍を持つ国立寺院として栄えます。
史跡下野薬師寺跡探索コース
奈良時代後半には、東大寺・筑紫観世音寺とともに正式な僧になるための場である戒壇(かいだん)が置かれ、国の仏教政策の一翼を担いました。
本コースは、整備された史跡下野薬師寺跡を徒歩で見学するコースです。
最初に、下野薬師寺跡のすべてがわかる「下野薬師寺歴史館」に立ち寄ってから探索するのがおススメです。
※各スポット名をクリックすると解説や動画を見ることができます。
※GoogleMapの精度の関係で、マップと現地の位置に誤差が生じます。
ご了承の上でご利用ください。民間信仰関連文化財群めぐり

本市で現在まで伝えられている民間信仰や祭礼は、近世以降に市内各地に広まりました。これらは社会情勢や生活習慣の変化に応じて形を変えながら、市内にある社寺とその周辺に住む人々を中心に継承され、本市の特徴的な歴史文化を表しています。
民間信仰関連文化財群めぐり
※各スポット名をクリックすると解説や動画を見ることができます。
※GoogleMapの精度の関係で、マップと現地の位置に誤差が生じます。
ご了承の上でご利用ください。中世城館関連文化財群めぐり

下野市は中世の下野国で名を馳せた武士、宇都宮氏と小山氏の勢力圏の狭間で支配をめぐり、数度にわたる戦闘が繰り返された地域です。進退をかけた戦闘の痕跡を示すように、市内各地には城館跡や関連する石造物が残されており、有力豪族(武士)の勢力の狭間で形成された本市の特徴的な歴史文化を表しています。
中世城館関連文化財群めぐり
※各スポット名をクリックすると解説や動画を見ることができます。
※GoogleMapの精度の関係で、マップと現地の位置に誤差が生じます。
ご了承の上でご利用ください。

- 1
- 2